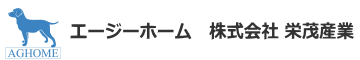みなさんこんにちは!エージーホームです。
2025年の「評価替え」が迫る中、固定資産税について不安や疑問を感じていませんか?
「固定資産税って、どうして毎年かかるの?」「評価替えって何?来年、税金が増えるの?」「自分の不動産の税金はこのままで大丈夫なのか不安……」――こうした声を足立区内の不動産オーナーの方々から多くいただきます。
この記事では、固定資産税の仕組みから、評価替えが税額に与える影響、そして節税のポイントや実践的な対処法まで、専門家の視点でわかりやすく解説していきます。特に、東京都内や足立区に不動産を所有している方にとって、地価の動向と評価替えの関係は、避けて通れない重要なテーマです。
この記事を読むことで、「評価替えで税金がどう変わるのか」「損をしないために今から準備すべきこと」「固定資産税の見直しや相談の方法」などが、具体的に理解できるようになります。
不動産を相続された方、空き家や土地を所有している方、売却や建て替えを検討中の方――そうした不動産オーナーの皆さまに、必ず役立つ内容となっております。ぜひ最後までご覧ください!
固定資産税とは?不動産オーナーが知っておきたい基礎知識
不動産を所有している限り、毎年納めなければならないのが「固定資産税」です。しかし、その内容を正しく理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。ここでは、不動産オーナーとして知っておくべき固定資産税の基本を解説します。
固定資産税はどんな税金なのか?
固定資産税とは、土地・建物・償却資産などの「固定資産」に対して課せられる地方税です。
この税金は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して、市区町村が課税します。例えば、東京都足立区内に不動産を持っている場合、足立区役所が納税通知書を送ってきます。
固定資産税は、地方自治体の貴重な税収源のひとつであり、道路や公園、公共施設の維持管理などにも活用されています。
課税される不動産の種類とは?
固定資産税が課せられるのは、主に以下の3つの資産です。
- 土地(宅地、農地、山林など)
- 家屋(住宅、倉庫、店舗など)
- 償却資産(事業用設備や機械など)
一般の不動産オーナーにとっては、主に土地と建物が対象となることが多いです。事業用の資産を持っている場合は、償却資産も対象に含まれます。
税額はどのように決まるのか?
固定資産税の税額は、以下の計算式で決まります。
課税標準額 × 税率(原則1.4%)= 税額
「課税標準額」とは、固定資産の「評価額」に基づいて市区町村が定めた金額です。評価額は国が定める基準に沿って決まり、原則として「再建築価格の70%程度」と言われています。ただし、住宅用地には軽減措置が適用されるため、実際の税負担は下がることもあります。
例えば、課税標準額が2,000万円の住宅ならば、基本の固定資産税は以下のようになります。
2,000万円 × 1.4% = 年額28万円
これに加えて、都市計画区域内では「都市計画税(上限0.3%)」もかかることがあります。足立区の場合、多くの地域が都市計画税の対象エリアです。
納税スケジュールと支払い方法
固定資産税は、毎年4〜6月頃に納税通知書が届きます。通常、年4回に分けて分割納付できる仕組みになっており、東京都足立区の場合も、以下のような期日で納付します。
- 第1期:6月初旬〜末
- 第2期:9月初旬〜末
- 第3期:12月初旬〜末
- 第4期:翌年2月初旬〜末
納付方法は、金融機関・コンビニ・口座振替・スマートフォン決済など、さまざまな方法が選べます。
「評価替え」とは何か?3年ごとの見直しが与える影響
固定資産税における「評価替え」は、税額の見直しが行われるタイミングであり、不動産オーナーにとって非常に重要な制度です。この制度を正しく理解することで、将来の税負担を見据えた資金計画や不動産活用の判断がしやすくなります。
評価替えとは?固定資産税評価額の見直し制度
評価替えとは、固定資産税の算出基準となる「評価額」を、3年ごとに見直す制度のことです。評価額は市場価格ではなく、総務省が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、市区町村が各不動産に対して個別に設定しています。
不動産の価格は、地価や建築資材の価格、地域の開発状況などに応じて変動します。そのため、3年ごとに全国一斉に評価額の見直しが行われ、より現状に即した評価額に調整されるのです。直近の評価替えは2022年に行われ、次回は2025年1月1日時点の価格を基準に実施されます。
なぜ3年ごとに見直されるのか?背景と目的
評価額を3年ごとに見直す理由は、税負担の公平性を保つためです。
たとえば、東京都足立区内で地価が上昇しているにもかかわらず、評価額が据え置かれていれば、実際の資産価値と税負担に乖離が生じ、不公平が生まれます。
また、不動産価格は景気やインフラ整備、再開発の影響を受けて急激に変化する場合もあります。そのような変化に対応し、課税のバランスを維持するために、3年ごとの評価替えが制度として設けられているのです。
評価額の変動は税額にどう影響するのか?
評価替えによって評価額が上がると、固定資産税の課税標準額も上がる可能性があります。
ただし、評価額が大きく変動しても、すぐに税額が大幅に増減するとは限りません。
理由は、以下のような**税負担調整措置(負担調整制度)**があるためです。
- 税額が急激に増えないように、段階的に上昇を抑制する措置
- 逆に、評価額が下がっても税額が急に減らないよう、調整する仕組み
たとえば、2022年の評価替えではコロナ禍の影響を受けて地価が一部下落したにもかかわらず、税額が大きくは下がらなかったケースが多くありました。このように、税金の額は評価額に連動しますが、必ずしも直線的な関係にはなっていないことを理解しておくことが重要です。
2025年評価替えに向けて注目すべきポイント
2025年の評価替えでは、コロナ明け以降の地価上昇傾向が反映される見通しです。特に東京都心から郊外にかけては、再開発や物流需要の高まりによって土地価格が上昇しているエリアも見られます。足立区においても、綾瀬、北千住、竹ノ塚などで再開発や区画整理が進行中です。
このような背景から、2025年の評価替えでは、一部地域の評価額が上昇し、固定資産税が増える可能性があります。特に地価上昇が著しいエリアに不動産を所有している場合は、来年以降の税負担を事前にシミュレーションしておくことが重要です。
東京都内の評価替えで税額が変動する理由
東京都内で不動産を所有している方にとって、評価替えによる固定資産税の変動は他地域よりも大きなインパクトを与えます。
なぜなら、都内の土地は全国的に見ても価格変動が大きく、再開発・インフラ整備の影響を受けやすいためです。
この章では、都内特有の評価額変動の背景を解説し、足立区における実例もご紹介します。
地価上昇が評価額に直結する構造
評価額は、市場の「地価公示」や「基準地価」などを参考に決定されます。
都内では近年、テレワークの普及や低金利、再開発などを背景に、住宅・商業地の地価が堅調に推移しています。
例えば、2024年に国土交通省が発表した基準地価(2024年9月時点)によると、東京都全体の住宅地は前年比で+3.5%、商業地では**+6.1%**の上昇が見られました。
評価替えではこのような実勢価格の変化が反映されるため、都内では税額の上昇リスクが高まる傾向にあります。
足立区の再開発・都市計画が与える影響
足立区も例外ではありません。近年の主な開発事業としては、以下のようなものがあります。
- 北千住駅周辺の再整備事業:大規模な駅前開発や大学キャンパスの進出により、住宅需要が拡大。
- 綾瀬駅エリアの再開発:老朽化した建物の建て替えや公共施設整備により、地価が上昇傾向。
- 竹ノ塚駅周辺の高架化完了とまちづくり推進:交通利便性の改善と新たな商業施設の開発。
これらの都市計画が進むことで、土地の評価額が上昇し、結果として固定資産税の増加につながる可能性があります。
2024年度の足立区の住宅地平均価格は、前年比**+4.2%**と23区の中でも高い伸び率を示しています(東京都都市整備局データより)。
評価替え後に税額が上がった実例
実際にあったケースとして、以下のような事例があります。
事例:綾瀬の戸建住宅所有者(地積:100㎡)
2022年時点の課税標準額:1,850万円
2023年地価上昇の影響を受けて、2025年評価額は2,050万円へ(+10.8%)
→ 固定資産税は年額25.9万円 → 28.7万円に上昇(+2.8万円/年)
このように、地価が10%程度上昇するだけでも、年間の税負担が2〜3万円単位で増えることは珍しくありません。これが複数物件を保有している場合、年間10万円以上の税額アップになる可能性もあります。
都市部では「負担調整」が効かないケースも
先述の通り、固定資産税には「税負担の調整措置」が設けられていますが、評価額が一定水準を超えた場合や、特例対象外となる資産では調整が効かないこともあります。特に、以下のようなケースでは注意が必要です。
- 住宅用地の面積が200㎡を超える部分(小規模住宅用地の軽減が部分適用)
- 貸し駐車場や空き地など非住宅用途の土地
- 商業地域の中の戸建て住宅(評価額上昇の影響を受けやすい)
足立区内でも、北千住や竹ノ塚駅周辺のように商業地への転換が進むエリアでは、住宅用地でも評価額が急上昇する可能性があります。
評価額が上がるとどうなる?実際の税負担と節税対策
評価額が上がると固定資産税も上がる――このような単純な理解では、不動産オーナーが損をしてしまう可能性があります。
税額の決まり方には複雑なルールや軽減措置が存在しており、正しく理解しないまま放置してしまうと、知らぬ間に数万円〜数十万円単位の損をしているケースもあります。
この章では、評価額の上昇がもたらす税負担の実際と、それに対する具体的な節税対策を紹介します。
評価額が上がると固定資産税も上がる可能性が高い
固定資産税の税額は「課税標準額 × 税率(原則1.4%)」で計算されます。
評価替えによって評価額が上がると、課税標準額も上昇し、それに伴って税額が増えるのが基本的な仕組みです。
ただし、すぐに税額が上がるとは限らず、以下のような調整が働きます。
【ポイント】負担調整措置とは?
固定資産税には「急激な税額上昇を避けるための緩和制度」として、負担調整措置が導入されています。
たとえば、急に評価額が上がっても、その上昇分の全てが翌年から課税対象になるのではなく、段階的に数年かけて反映されるようになっています。
ただし、以下のような条件に該当する不動産では、調整措置が働かず、評価額の上昇=税額アップに直結します。
- 新築住宅で軽減措置が終了した直後
- 貸し駐車場や非住宅用の更地
- 都市計画税が別途課税される地域
- 特例対象から外れた高額資産
東京都足立区内では、空き家や相続後の更地になった土地で固定資産税が大幅に上昇したケースも確認されています。
不動産オーナーが使える節税対策
固定資産税には、正しく申請すれば節税につながる特例・軽減措置がいくつも用意されています。
ここでは主なものを紹介します。
小規模住宅用地の特例(住宅用地の課税標準の特例)
住宅が建っている土地については、以下のような軽減措置があります。
- 200㎡以下の部分:課税標準が1/6に軽減
- 200㎡を超える部分:課税標準が1/3に軽減
たとえば、足立区内で150㎡の土地に住宅を建てている場合、その評価額が2,400万円だとしても、課税標準は実質400万円(2,400万円 ÷ 6)程度に抑えられる可能性があります。
この制度を活用すれば、同じ評価額でも土地に住宅があるかないかで税額が大きく変わることになります。
新築住宅に対する税額軽減措置
個人が自己居住用として住宅を新築した場合、以下のような減税制度があります。
- 床面積50㎡以上280㎡以下の住宅が対象
- 3年間(長期優良住宅は5年間)にわたり、固定資産税の1/2が減額される
足立区内で新築戸建てを建てた方の中には、この制度によって年間10万円以上の税負担を軽減できたケースもあります。
老朽空き家の特例解除に注意!
相続や転居により放置された空き家では、固定資産税の軽減特例が解除されるケースがあります。
具体的には、以下のような状態の空き家が該当します。
- 建築基準法の耐震基準を満たさない
- 外壁の剥がれや屋根の崩壊など危険性がある
- 長期間使用されていない状態が明らか
このような空き家では「住宅用地」の扱いから外れ、小規模住宅用地の軽減が適用されなくなるため、固定資産税が3〜4倍に増えることもあります。
節税だけでなく「戦略的な資産活用」も重要
節税対策を講じることは大切ですが、単に税金を抑えることだけが目的になってしまうと、不動産の価値を最大限に活かせない可能性があります。
たとえば…
- 賃貸物件に活用して収益化すれば、税金を上回る収益を確保できる可能性
- 更地を売却することで、将来の税負担を回避しつつ現金化
- 不動産管理会社に委託して、空き家の維持費と税負担のバランスを最適化
このように、「評価額が上がった=損」と考えるのではなく、上がった価値をどう使うかが、不動産経営の鍵になります。
プロが教える!固定資産税の確認方法と見直しのポイント
評価額や固定資産税の内容に不安や疑問がある場合、確認方法や見直し方法を知っておくことがとても重要です。
特に、2025年の評価替えに向けては、「納税通知書の見方」「不服申立ての方法」「専門家に相談するタイミング」などを把握しておくことで、無駄な税負担を避けることができます。
この章では、不動産の専門家であるエージーホームの視点から、実務に役立つ確認ポイントを紹介します。
納税通知書のチェックポイント
毎年4月から6月にかけて送付される「固定資産税・都市計画税 納税通知書」には、課税明細が細かく記載されています。
しかし、多くの方が内容を詳しく確認せず、そのまま支払ってしまっているのが現状です。
確認すべき主なポイントは次のとおりです。
- 所在地や地番が所有している物件と一致しているか
- 課税標準額・評価額が前年と比べて変動していないか
- 軽減措置や特例の適用状況が正しく記載されているか
- 税額の内訳(固定資産税/都市計画税)が正確かどうか
例えば、評価額が上がったのに「小規模住宅用地の特例」が適用されていないことで、税額が2倍以上になっていたという実例もあります。
納税通知書はただの請求書ではなく、不動産オーナーにとって「評価内容を確認するための通知」でもあるのです。
固定資産課税台帳の閲覧方法
より詳細な評価内容を確認したい場合は、「固定資産課税台帳」を閲覧することで、個別の評価額や算定根拠を確認できます。
足立区を含む東京都内では、各区の区役所(資産税課)で以下の手続きにより閲覧が可能です。
- 必要書類:本人確認書類(運転免許証など)・所有者確認資料(登記簿謄本など)
- 閲覧可能期間:毎年4月初旬〜6月末頃(評価替えの年は閲覧期間が延長される場合もあり)
- 閲覧手数料:無料または100円程度(自治体により異なる)
この台帳を閲覧すれば、隣地との評価額比較も可能になり、不公平な評価がされていないかのチェックにもつながります。
評価額に納得できない場合の「不服申立て」とは?
「評価額が明らかに高すぎる」「近隣よりも税負担が大きい」という場合は、「不服申立て(審査の申出)」を行うことが可能です。
不服申立ての概要は以下の通りです。
- 提出先:資産の所在地の固定資産評価審査委員会(足立区の場合は足立区役所内)
- 提出期限:納税通知書の送付日から3か月以内
- 提出書類:審査申出書、証拠書類(近隣の評価額情報など)
- 審査結果が出るまでに数か月かかることもある
この手続きを通じて、評価額が適正でないと判断されれば、翌年以降の税額が修正される可能性があります。ただし、評価基準は明確なため、申立てには専門家のサポートがあるとより有利です。
こんなときは不動産のプロに相談を
次のような状況では、不動産会社や税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
- 評価額が急に上がって理由が分からない
- 複数の不動産を相続し、課税内容が複雑になっている
- 空き家の維持と税負担で悩んでいる
- 売却や賃貸に切り替えたほうが良いか判断が難しい
足立区を拠点とするエージーホームでは、実際の評価額の妥当性チェックから、納税通知書の読み方、節税方法、空き家活用のご提案まで、ワンストップでご相談をお受けしております。
まとめ
ここまで、固定資産税の基本、評価替えの仕組み、東京都内・足立区の最新事情、評価額上昇時の税負担と節税対策、さらには見直しの実務まで幅広く解説しました。
固定資産税は、不動産を所有している限り毎年ついて回る重要なコストです。特に、2025年の評価替えに向けては、地価上昇や制度の変化を的確に理解し、早めの対策を講じることが求められます。
評価額が上がっても、制度を活用すれば税額の上昇を抑えることができ、場合によっては見直しによって不当な負担を軽減できる可能性もあります。
エージーホームでは、東京都足立区を中心とした関東エリアで、空き家・建て替えから売却・賃貸のお手伝いまで幅広くおこなっております。是非!不動産の事ならエージーホームにお任せください!